「これが燃料電池の量産ラインだ」,米Medis社が製造設備を公開 - 電子部品テクノロジ - Tech-On!
月産150万個!ですか??
この規模なら、まさに量産ラインと言って良いでしょう。
ポータブル充電器と言うことは、燃料電池で直接機器を動作させるわけではないようですね。
携帯電話等の充電器として利用するようですね。
確かに、いくら小型といっても、携帯電話に組み込めるような大きさではなさそうです。
「これが燃料電池の量産ラインだ」,米Medis社が製造設備を公開 - 電子部品テクノロジ - Tech-On!
気になる燃料ですけど、メタノールではなくボロハイドライドを使うようです。
どうやって?燃料を手に入れ、交換するのか?
このあたりに、まだ疑問は残りますね。
出力は1W、まだまだ二次電池に頼らざるを得ない感じなんでしょうかね?
▼ボロハイドライドとは - NE用語 - 日経エレクトロニクス - Tech-On!用語辞典
「これが燃料電池の量産ラインだ」,米Medis社が製造設備を公開
自動化ラインで製造される燃料電池利用のポータブル充電器「Power Pack」
搬送される燃料電池セル。上面に,DC-DCコンバータなどを実装した回路基板が載っている
続々と生産中
米Medis Technologies Ltd.は,燃料電池を用いるポータブル充電器の生産を,アイルランドのGalwayで開始した(製造ラインの公開動画を含むページ)。アイルランドCelestica社の製造設備内に,専用の製造ラインを構築した。
月産150万個の製造能力がある。2007年末までに月産100万個規模で出荷する予定。
月産150万個!ですか??
この規模なら、まさに量産ラインと言って良いでしょう。
ポータブル充電器と言うことは、燃料電池で直接機器を動作させるわけではないようですね。
携帯電話等の充電器として利用するようですね。
確かに、いくら小型といっても、携帯電話に組み込めるような大きさではなさそうです。
「これが燃料電池の量産ラインだ」,米Medis社が製造設備を公開 - 電子部品テクノロジ - Tech-On!
量産を開始した「24-7 Power Pack」は,水素とホウ素の化合物であるボロハイドライドを燃料に使う。
燃料の供給にポンプなどを用いない,いわゆるパッシブ型の燃料電池で,電圧5V,電流220mAで約1Wの出力がある。Medis社によれば,Power Packは27種類の部品で構成されているという。
Medis社はこのPower Packを,携帯電話機や携帯型ゲーム機,PDAなどの充電用途に向けている。
気になる燃料ですけど、メタノールではなくボロハイドライドを使うようです。
どうやって?燃料を手に入れ、交換するのか?
このあたりに、まだ疑問は残りますね。
出力は1W、まだまだ二次電池に頼らざるを得ない感じなんでしょうかね?
▼ボロハイドライドとは - NE用語 - 日経エレクトロニクス - Tech-On!用語辞典
ボロハイドライド
読み:ボロハイドライド
ボロハイドライド(NaBH4)は水と反応して水素を発生するため,燃料電池に供給する水素の貯蔵材料として利用できる。原料はNa2B4O7(ホウ砂)であり,ここからNaBO2(二酸化ホウ素ナトリウム)を誘導し,水素化してNaBH4を得る。

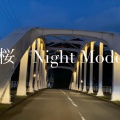


















2006年4月に米国での携帯機器の展示会で無料配付されていたものです。
2006.10.23日経エレクトロニクスに分解写真などが掲載されています。
中和用の部材など、使い捨てならではの技術を使ってローコストを実現しているようです。